John Henry Bonham #5 最終回
結構長くなってきたボンゾシリーズ。
それでもまだまだほんの上っ面ですが・・(^_^;)
それでもまだまだほんの上っ面ですが・・(^_^;)
(前回John Henry Bonham #4→)
サウンドとは、ミュージシャンとエンジニアとスタジオ、そしてプロデューサーと共に作り上げられる、と前回お話ししました。
その時説明した通り、Led Zeppelinの記念すべき第1作「Led Zeppelin I」は、プロデューサー=ジミー・ペイジ、エンジニア=グリン・ジョンズ、スタジオ=オリンピックスタジオ、というチームで作り上げたサウンドです。
ただ、この頃のジミー・ペイジは、ミュージャンとして、アレンジャーとしては既に長い経験もあり一流でしたが、サウンドプロデュースに関しては、まだまだ勉強中で、ほぼ、エンジニア任せだったと推察できます。(根拠は、読み進んでいただければわかると思います)
故に、その後、グリン・ジョンズとの間で、プロデュース権で揉めたのだと思います。
(グリン・ジョンズは、書籍等ではジミーのことを悪く言ったりすることはありませんが、実際は口も利きたくない間柄らしいwww)
といったことを踏まえつつ、私的には、ミュージシャンとしてもエンジニアとしても大きな影響を受けた名盤、2nd「Led Zeppelin II」からボンゾサウンドを紐解きます。
前作「Led Zeppelin I」では、全曲通じて、グリン・ジョンズによる、録音及びミキシングでしたが、今作では、全米ツアー中ということもあり、ロンドンだけでなくニューヨークでも複数のスタジオで録音され、エンジニアも複数担当しています。
それをまとめ上げたのは、ジミ・ヘンドリクス等で名を上げた、名匠、エディ・クレイマーです。
まずは、レコーディングを担当したのは、ロンドンのオリンピックスタジオにてジョージ・チキアンツによる「Whole Lotta Love」「What is and What Should Never be」の2曲、LAのミラー・サウンドにてクリス・ヒューストンによる「The Lemon Song」「Moby Dick」の2曲、ロンドンのモーガンスタジオにてアンディ・ジョンズ(グリン・ジョンズの実弟)による「Thank You」「Living Loving Maid」の2曲、ニューヨークのA&Rスタジオにてエディ・クレイマーによる「Heartbreaker」「Ramble On」「Brin it on Home」の3曲、以上9曲です。
エンジニアそれぞれによる違いを聞き取ることができます。
特に、アンディ・ジョンズのサウンドには他と違う個性を感じます。
それでは、ハイライトでもある「Whole Lotta Love」(`69発売)を聞いてみましょう。
同じエディ・クレイマーによる、ジミ・ヘンドリックス&エクスペリエンスの「Little Wing」('67発売)のサウンドとの比較も興味深いです。
二曲とも、とても素晴らしい録音とミックスだと思います。
(エクスペリエンスの)ミッチ・ミッチェルの、ジャズドラマーがロックやってる感が面白いです。
この時代のドラマーは、こんな感じの人が多いですね。ジャズから入った人とかジャズドラマーに強く影響を受けた人。
(ボンゾも、影響を受けたドラマーの一人にジャズの名ドラマー、バディ・リッチを挙げています)
何が違うのかというと、簡単に言うと、ジャズドラマーにとってバスドラとスネアとは、リズムをリードするというより、アクセントのためにのもの、という意味合いが強いと思いますし、おかずもカラフルで手数も多いです。
反面、アクセントメインの為、基本ビートが軽いというか弱いというか・・・
まぁ、ビート自体のインパクトが弱いキライがあります。
抑揚が大きい、とも言えますが・・・
ところがそこに、強烈なバスドラと2拍4拍のスネアのバックビートを効かせたリフ中心のプレイを押し出したRock'n Rollという新しい音楽が登場します。
その代表格が、THE BEATLESのリンゴ・スターです。
彼の独特の8ビートは格別です。おかず(フィルイン)も最低限ですね。
この後、ロックドラムの概念は大きく変革していきます。
ゼップ、ジミどちらのサウンドも時代を超える普遍性を持っています。
ただ、このアルバムにおけるドラムサウンドは、一枚目とは違う部分もありますが、まだまだその延長線上にあります。
基本、3~6本程の少ないマイクで録音され、ミックスも、EQ、Comp、Reverb、Delayによる軽い処理です。
さて、今回はさらに話を進めましょう。
続く3枚目とそれ以降(III〜フィジカル・グラフィティ)では、大きくそのレコーディング方法を変革します。
これは、ジミー主導によるものと思って間違いないと思います。
その頃も現在も、基本、レコーディングとは、そのために設計されたスタジオで行うものですし、その方が良いサウンドになる、という考え方が一般的です。
ところが、もう一つのレコーディング方法、出張レコーディングもかなり古くから存在しました。
イギリスでも、1920年代からオーケストラレコーディングの際に使用されてきたようです。
より現代的な、所謂マルチトラックレコーディングによる出張レコーディングが可能になったのは、やはり1960年代になってからです。
特に、ローリングストーンズが所有したローリング・ストーンズ・モービル(RSモービル)の登場は大きかったようです。
元々、The Beatlesによって為されたレコーディング革命(アーティストが好きな時に好きなだけスタジオを使用できる)により、膨らみまくるスタジオ使用料を削減するために自前のスタジオ(アップルスタジオ)を建設したことが、ライバルバンドのローリングストーンズに衝撃を与えました。特に、財政担当とも言えるミック・ジャガーに。
誰にも(本人すら)ゴールが見えない永遠に続くリフの繰り返しを求めたキース・リチャーズにうんざりしていたミック・ジャガーは、渡りに船と購入したばかりの邸宅にスタジオの建設を考えます。
その計画の中で、オリジナルメンバーでありロードマネージャーだったイアン・スチュアートがトラックの中に全てを備えたモービル・レコーディング・カーを思いつきます。
ミックの邸宅のみならず、好きな時に好きな場所、ライブ会場でさえ録音可能になります。
このアイディアに、ゴーサインが出たのは当然でしょう。
このRSモービルは、その後、数々の名盤のレコーディングで大活躍することになります。
このモービルに備えられたコンソールもまた、ヘリオス、でした。
(Rolling Stones、Led Zeppelin、Deep Purple、Bad Company、Bob Mariy、Neil Youngその他多数)
このニュースを聞いたジミーは、1年半に及んだ超長期ツアーの終了後、休養も兼ねながら、メンバー共々田舎の邸宅でゆっくり過ごしながら、RSモービルを使用して好きな時に好きなだけレコーディングするという計画を思いつきます。
ここでのプロデューサー、ジミー・ペイジは、あくまでも、曲作りとメンバーのリラックスした演奏を引き出すための演出として、出張レコーディングを採用したのだと思います。
ところが、偶然にもこの時使用された大邸宅「ヘッドリィ・グランジ」でのサウンドが、後々、ボンゾのドラムサウンドに決定的な個性を与えることになります。
III、Ⅳ、に収められた全18曲中、2曲を除き(III、Gallowa Pole - エディ・クレイマーミックス。Ⅳ、The Battle of Evermore - ジョージ・チキアンツ ミキシング)、全て、アンディ・ジョンズ一人による録音、ミキシングです。まずは、1970年発表のIIIより「Out on the Tile」。翌1971年発表のⅣより「Misty Mountain Hop」。
この、Misty Mountain Hopと、おそらく全く同じ方法で録音されたと思われるのが、ボンゾサウンドとしてつとに有名なWhen the Levee Breakesです。
二曲とも、ヘッドリィ・グランジの玄関ホールにセットされたドラムを、吹き抜けの階段上にセットされた二本のBeyerdynamic(ベイヤーダイナミック) M160というリボンマイクでステレオ収録され、ヘリオスコンソール内蔵のコンプレッサー、F760で強力に圧縮され録音されて、吹き抜けの玄関ホールに響き渡るドラムサウンドを、さらに強力にしたようです。
リボンマイクとは、ダイナミックマイクでありながら、コンデンサーマイク並みにフラットな周波数を持ち、その質感は、より自然です。昔から、ドラムトップに常用されていました。
もちろん、高い天井の洋館特有の深いリバーブ付きです。
違いは、When the Levee BreakesにはBinson Echorecというドラム式エコー(ディレイ)がかけられているところでしょうか。ドラム全体かけられた16分程度のディレイが真ん中から聞こえますね。
ジミー・ペイジ本人の言葉によると、この時、ボンゾは、真新しいLudwig社製のグリーンスパークルのセットが届いたようで、バンドのセッティングが玄関隣のメインルームで行われている最中に、待ちきれないとばかりに、玄関ホールにセットして叩き出したサウンドを耳にしたジミー・ペイジが、思わず「これだ ! これを使おう ! 」と言って録った、らしいです。
Misty Mountain Hop、When the Levee Breakesの2曲では、これまでと違う点がまだあります。
おそらく、マイク二本だったことが一つの理由だったと思いますが、これまでのミックスに比べて、より深くコンプレッサーが掛かっています。
それまでのコンプ処理は、音色加工というより、あくまでも、レベル抑制だったり音圧アップが目的だった気がします。
つまり。コンプを使っても、遅いアタックとリリースで、より音色変化の少ないセッティングだったと推察できます。
この逆のセッティングにすると、いわゆる潰れたコンプサウンドになり、下手すればグシャグシャの破綻したサウンドになります。
ドラムの迫力を増しながら、破綻させないためには、アタック遅めでリリース速めのセッティングになります。
この時代、迫力を出す目的としては、前回でも解説したように、どちらかというと、テープコンプや歪みを利用することが多かったように思います。例えば、初期クイーンのプロデュースを担当した、ロイ・トーマスベイカーは、歪みを扱う名人でした。クイーンのドラムを聞くと、ほとんど歪んでいることがわかると思います。
しかし、ここでは、いわゆる現代に通じるようなコンプ感を聞き取ることができます。
たまたまHelios F760がそういう音だったのか? アンディ・ジョンズのアイディアなのかはわかりません。
また、ドラムのマルチトラックテープ再生スピードを落としているようです。
再生スピードを落とすと、当然、キーが下り、それに伴い余韻も伸び、周波数特性が下がることによりアタックも太くなります。
これも、単にテンポが早い、と感じたからなのか? サウンドの迫力を出すため、なのか?
誰も発言していないので謎のままです。(秘密を知る二人のうちアンディ・ジョンズは既に他界)
(この時代、テープスピードを上下させて、キーを変更したりサウンドのニュアンスを変化させる事は頻繁に行われていました。)
もう一つ不思議に思うことは、なぜ、2本ステレオで録音しているのに、片側へ音像が偏っているんだろうか ?という点です。
当時のドラム定位は、今のように真ん中にどっしり、という概念が固定される前だとはよくわかっていますが(実験ともいうwww)、せっかく2本でステレオ収録しているのになぜ?と思うわけです。勿体無い。
いずれにしても、ボンゾが叩き出す圧倒的なサウンドと、これらすべての相乗作用により生み出されたサウンドだと言えます。
この時代のロックは、少ない機材から、ありとあらゆる可能性を引きずり出して新しい革新的なサウンドを作り出そうと、誰もが必死に切磋琢磨してサウンドを創造していたんですね。なんと素晴らしい時代!
しかし、それにしても、たった二本でこのサウンド ! ! ! !
ボンゾだからこそ可能なサウンドです。
他のドラマーでは、なかなかこうはなりません。
これこそが唯一無二のツェッペリンサウンドだと。
というのも、この、いわゆるアンビエント(アンビエンス)ドラムサウンドが、この後のアルバムでも、ここ一発の場面で登場するわけですが、時代は70年代真っ只中、ドライかつクリアーで各パーツが点で見えるようなサウンドが主流の時代に、まるで、そこに立ちふさがるかのように、巨大な塊の面で押しまくるようなサウンドで最後まで勝負したのがLed Zeppelinだからです。
※アンビエンスとは、環境音の事。レコーディング用語としては、もっぱらルームサウンド(部屋の響き)の意として使われることが多い。
(しかし、このサウンドに関しては、これまで様々な憶測による解説が出てましたが、全て外れてましたねwww。例えば、ツェッペリンが宿泊していたホテルの非常階段の踊り場で録られた、とか。信じてたな〜www
しかも、意外なほど狭い。
ヘッドリィ・グランジが郊外の大邸宅と知った時も、最低でも30畳くらいの面積と、10mくらいの高さの天井を想像していましたwwww。)
皮肉なことに、80年にボンゾが天国へ召されツェッペリンも解散した後の80年代には、まるで、ボンゾサウンドを追いかけるようなアンビエントサウンドの大流行になります。
しかし、そのいずれもが、ボンゾサウンドには程遠い、と個人的には思います。
この80年代は、100chに及ぶ入力、チャンネル毎のGate&Comp、セッティングリコール等まで装備した超多機能コンソールやデジタルリバーブの登場で、多種多様なエフェクトが同時に何種類も使用することが可能になり、ルームアンビエンスと混ぜ合わせた強力なドラムサウンドが音楽シーンを席巻した時代です。それでも、原音の差は如何ともし難いものがあるのだと思います。
この当時、百花繚乱のバンドシーンの中でも異彩を放ち、たった一枚で解散したPower Stationの1985年の作品「Get It On (Bang a Gong) 」。
これ、夭折の天才マーク・ボラン率いるT-Rexが1971年に発表した作品のカバーですが、原曲同様めちゃくちゃかっこいいっす。
このバンドのドラマー、トニー・トンプソンは、あのシックのメンバーで、当時最高のドラマーの一人でした。
どうでしょう? ボンゾと比べて・・・
因みに、エンジニアは、ジェイソン・カサロ、スタジオは当然パワーステーションです。
因みついでに、このトニー・トンプソン、地球規模のチャリティーショー、USA for Africa('85)のLed Zeppelin再結成時のドラマーをフィル・コリンズと共に務めました。バンド自体の出来は散々でしたね。ジョン・ポール・ジョーンズは相変わらずの達者ぶりでしたが、なんせフロントの二人が・・・・・言うまい(T . T)
いよいよ、終盤です。
えっ? まだ4枚目じゃん、というツッコミはごもっともですが、この4枚を持って、ジミー・ペイジは、あらかた、自分たちにピッタリのレコーディング方法の全てを会得したのだと思います。
つまり、70年代も中盤以降になると、ロックは巨大産業化し、それに伴い、いわば先逹の弟子ともいうべき優秀なエンジニアも増え、機材も進化し、プロデューサーのサウンド志向がはっきりしているのであれば、もはや、誰と何処で録っても、望むサウンドが出せるようになったということです。
(個人的には、現代ロック(特にハードロック)エンジニアリングは、IIから担当したエディ・クレイマー、III、Ⅳを担当した、アンディ・ジョンズ、それと、ツェッペリンとは一切関わりありませんが、ディープ・パープルやレインボー、アイアン・メイデン等を担当したマーティン・バーチの三人によってその基礎が形作られたように思っています。あっ、ビートルズの、ジェフ・エメリック入れないといかんですね〜。それとT-Rexではエンジニア、クイーンではプロデュースを担当したロイ・トーマス・ベイカーとクイーンやジャーニーのエンジニア/プロデューサーを務めたマイク・ストーンも忘れちゃいけませんね。
えーっと他にも・・・人数限定は無理っすねwwww)
Ⅳの次の「永遠の詩」は、再度エディ・クレイマーを起用していますが、続く、「フィジカルグラフィティ」も、一曲を除き(「House of Holy」録音ミックスともにエディ・クレイマー)、録音は、エンジニア、場所は様々ですが、ミックスエンジニアは、全てキース・ハーウッドが担当しています。
(個人的には、House of Holyのサウンドが一番好きですがwww)
「Presence」では、前作に続き、キース・ハーウッドが録音ミックスの全てを担当していますし、スタジオもドイツのMusiclandを使用しています。
それでも、サウンドの個性はまさにツェッペリンそのものです。
ここでは、「フィジカルグラフィティ」から、「Kashmir」。録音場所は、あの、ヘッドリィ・グランジ、エンジニアは、ロン・ネヴィソン。まさにここ一発のサウンドを使ってます。が、よく聞くとわかりますが、当然録音方法は違っています。
おそらく、各パーツ毎にクロースマイク(オンマイク=近接マイク)をセットした上で、離れた場所に置いたアンビンエンスマイクを立てて録音し、軽くフランジャーかフェイザーを掛け、ミックスするというまさに現代的な手法で仕上げられていると思います。
それでも、ボンゾはボンゾです。
では、「フィジカルグラフィティ」から「Kashmir」続けて「Presence」より「Nobody's Fault but Mine」
ミックスエンジニアが同じということもありますが、実によく似たサウンドになっていますね。
この時のエンジニア、キース・ハーウッドは、多忙のあまり、77年に居眠り運転で事故死されます。まさに売れっ子エンジニアになって、さあこれからという時でしたのでさぞや無念だったことでしょう。
書きながら思い出しましたが、80年代といえば、1988年にツェッペリンにまつわるちょっとした騒ぎがありました。
ある日のFMから突然流れてきたある曲が、「Kashmir」そっくりだったんです。
特に、リフとボーカル ! ! 一瞬、プラントの喉が治って再結成したのかと思ったほどです。しかも、その番組のホストは、あの熱狂的ツェッペリンフリークで有名な渋谷陽一氏だったので尚更です。
既に、世界的に話題沸騰中だったようです。
この騒動の主は、Kingdom Comeという新人バンドでした。
プロデューサーは、カナダ人のボブ・ロック。
彼は元ギタリストですが、サバイバーやラヴァーボーイ、エアロスミス等のエンジニア活動を経て、プロデューサーになった人で、メタリカやモトリークルーの大ヒットで大成功を収めます。エンジニアとしてもプロデューサーとしても大変優秀な人のようです。
サウンド傾向は、80年代を象徴する派手でエフェクトたっぷりの、まさに産業ロックそのものです。貶しているわけではありません。プロの世界は売れてナンボです。
意外なところでは、スタンダードジャズボーカルの旗手、マイケル・ブーブレも担当しているところです。個人的に大好きなシンガーです。
スタンダードジャズだけでなく、懐かしい感じのR&Bや、ビートルズっぽいポップスまで幅広いスタイルの持ち主です。懐の深いプロデューサーなんですね。
また脱線しました。😓
Kingdom Comeは、その余りにツェッペリンを彷彿させる曲調とボーカルによってか、世界中で大ヒットしました。
ところが、内容も演奏も中々良かったにも関わらず、結局似過ぎていた事が仇となり、叩かれるだけ叩かれて、結局2枚のアルバムを出しただけで消えて行きました。
神に近づき過ぎると火傷するということなのでしょうか ?
まるでイカロスのように?😆
このバンドのドラマーはなかなか優秀だったようで、その後も、様々なバンドで活躍したようです。(2016年まで、スコーピオンズに在籍)
まさに産業ロック全盛の80年代末期にあらゆるスタジオ機材を駆使して挑んだツェッペリンサウンド、お楽しみいただければ幸いです。
KINGDOM COMEファーストから「Get it On」
さて、いよいよオーラスです。
ここまでくると、なぜ、ジョン・ヘンリー・ボーナムこそがロック史上最高のドラマー、という自論を持つに至ったのか、なんとなくご理解いただけたのではないでしょうか?
彼のドラムサウンドは唯一無二(しかも、世界中のロックドラマーが憧れ追求しているにもかかわらず誰も近づけない)かつ、同時にバンドそのものを体現しました。
こんなドラマーとバンドは、もう二度と出ないでしょう。
もちろん、彼より上手いドラマーなどいくらでもいるでしょう、違う意味で素晴らしいサウンドのドラマーも。
しかし、誰一人として彼のような並外れたサウンドは出せません。
彼のように、自らのサウンドがバンドサウンドを体現したドラマーも思い当たりません。
故に、彼をしてロック史上最高のドラマーだと思うのです。
最後に、彼ら最後のオリジナルアルバム「In Through the Out Door」('79)より、彼が敬愛したドラマー、バーナード・パーディー(単にドラマーとなれば、No1の筆頭)がプレイしたスティーリー・ダンのアルバム「Aja」収録の「Home at Last」(カッケー!)にインスパイアされたといわれる「Fool in the Rain」。
因みに、この二曲に、TOTOの名ドラマー、ジェフ・ポーカロがインスパイアされて生まれたのが「Rosanna」だということは有名な話。
(久しぶりに聞いた「Home at Last」があまりにかっこよかったので、これも添付します)
レコーディング、ミキシングともにエンジニアはレイフ・マセス。
スタジオは、レコーディングがポーラー・スタジオ。ミキシングが、プランプトン・スタジオ。共にスウェーデンです。
このサウンドが、When the Lebee Breakesと並んで、ボンゾサウンドの代名詞だと言われているようですが、もはや、イギリスのスタジオでもエンジニアでもありません。
かくて、最後のアルバムにしてジミー・ペイジ プロデュースはついに確立したのです。
※ あくまでも個人的見解ですが、Led Zeppelinとは、まさにそのサウンドそのものが本体なのだと思います。勿論、メロディやアレンジ、詞、演奏こそが音楽ではないか ! というごもっともなご意見にも大いに賛同しますが、Led Zeppelinに関しては、これだけでは当てはまらないと思います。
デビュー当時から散々批判された、ブラックミュージックからの、詞、メロディ等の限りなくアウトに近い引用(パクリともいう)の数々(裁判ではかなり敗訴したらしいwww)。
しかし、比べてみれば一聴瞭然、その圧倒的サウンドにひれ伏してしまうのです。
まさに、誰にも出せないサウンドがそこにあります。
勿論、バンドの成長とともに楽曲も大いに発展を遂げ、Ⅳの頃には、これぞLed Zeppelinという楽曲が生まれていました。
それでも、ツェッペリンの本質はサウンドであると確信します。
そして、その中心にいたのがボンゾのドラムでした。
もし、この駄文を最後まで読んでいただいた方がいらっしゃったのでしたら、心から感謝申し上げます、ありがとうございました。
これに懲りず、また覗いてやってください。相も変わらずマニアックネタだとは思いますがwww
サウンドとは、ミュージシャンとエンジニアとスタジオ、そしてプロデューサーと共に作り上げられる、と前回お話ししました。
その時説明した通り、Led Zeppelinの記念すべき第1作「Led Zeppelin I」は、プロデューサー=ジミー・ペイジ、エンジニア=グリン・ジョンズ、スタジオ=オリンピックスタジオ、というチームで作り上げたサウンドです。
ただ、この頃のジミー・ペイジは、ミュージャンとして、アレンジャーとしては既に長い経験もあり一流でしたが、サウンドプロデュースに関しては、まだまだ勉強中で、ほぼ、エンジニア任せだったと推察できます。(根拠は、読み進んでいただければわかると思います)
故に、その後、グリン・ジョンズとの間で、プロデュース権で揉めたのだと思います。
(グリン・ジョンズは、書籍等ではジミーのことを悪く言ったりすることはありませんが、実際は口も利きたくない間柄らしいwww)
といったことを踏まえつつ、私的には、ミュージシャンとしてもエンジニアとしても大きな影響を受けた名盤、2nd「Led Zeppelin II」からボンゾサウンドを紐解きます。
前作「Led Zeppelin I」では、全曲通じて、グリン・ジョンズによる、録音及びミキシングでしたが、今作では、全米ツアー中ということもあり、ロンドンだけでなくニューヨークでも複数のスタジオで録音され、エンジニアも複数担当しています。
それをまとめ上げたのは、ジミ・ヘンドリクス等で名を上げた、名匠、エディ・クレイマーです。
まずは、レコーディングを担当したのは、ロンドンのオリンピックスタジオにてジョージ・チキアンツによる「Whole Lotta Love」「What is and What Should Never be」の2曲、LAのミラー・サウンドにてクリス・ヒューストンによる「The Lemon Song」「Moby Dick」の2曲、ロンドンのモーガンスタジオにてアンディ・ジョンズ(グリン・ジョンズの実弟)による「Thank You」「Living Loving Maid」の2曲、ニューヨークのA&Rスタジオにてエディ・クレイマーによる「Heartbreaker」「Ramble On」「Brin it on Home」の3曲、以上9曲です。
エンジニアそれぞれによる違いを聞き取ることができます。
特に、アンディ・ジョンズのサウンドには他と違う個性を感じます。
それでは、ハイライトでもある「Whole Lotta Love」(`69発売)を聞いてみましょう。
同じエディ・クレイマーによる、ジミ・ヘンドリックス&エクスペリエンスの「Little Wing」('67発売)のサウンドとの比較も興味深いです。
二曲とも、とても素晴らしい録音とミックスだと思います。
(エクスペリエンスの)ミッチ・ミッチェルの、ジャズドラマーがロックやってる感が面白いです。
この時代のドラマーは、こんな感じの人が多いですね。ジャズから入った人とかジャズドラマーに強く影響を受けた人。
(ボンゾも、影響を受けたドラマーの一人にジャズの名ドラマー、バディ・リッチを挙げています)
何が違うのかというと、簡単に言うと、ジャズドラマーにとってバスドラとスネアとは、リズムをリードするというより、アクセントのためにのもの、という意味合いが強いと思いますし、おかずもカラフルで手数も多いです。
反面、アクセントメインの為、基本ビートが軽いというか弱いというか・・・
まぁ、ビート自体のインパクトが弱いキライがあります。
抑揚が大きい、とも言えますが・・・
ところがそこに、強烈なバスドラと2拍4拍のスネアのバックビートを効かせたリフ中心のプレイを押し出したRock'n Rollという新しい音楽が登場します。
その代表格が、THE BEATLESのリンゴ・スターです。
彼の独特の8ビートは格別です。おかず(フィルイン)も最低限ですね。
この後、ロックドラムの概念は大きく変革していきます。
ボンゾのドラムは、まさにこの発展系です。
エディ・クレイマーというエンジニアは、とにかく空間表現に優れた方で、リバーブ、ディレイ、パンを駆使した音像構築に多大な影響を受けました。ゼップ、ジミどちらのサウンドも時代を超える普遍性を持っています。
ただ、このアルバムにおけるドラムサウンドは、一枚目とは違う部分もありますが、まだまだその延長線上にあります。
基本、3~6本程の少ないマイクで録音され、ミックスも、EQ、Comp、Reverb、Delayによる軽い処理です。
Led Zeppelin 「Whole Lotta Love」
The Jimi Hedrix Experience「Little Wing」
さて、今回はさらに話を進めましょう。
続く3枚目とそれ以降(III〜フィジカル・グラフィティ)では、大きくそのレコーディング方法を変革します。
これは、ジミー主導によるものと思って間違いないと思います。
その頃も現在も、基本、レコーディングとは、そのために設計されたスタジオで行うものですし、その方が良いサウンドになる、という考え方が一般的です。
ところが、もう一つのレコーディング方法、出張レコーディングもかなり古くから存在しました。
イギリスでも、1920年代からオーケストラレコーディングの際に使用されてきたようです。
より現代的な、所謂マルチトラックレコーディングによる出張レコーディングが可能になったのは、やはり1960年代になってからです。
特に、ローリングストーンズが所有したローリング・ストーンズ・モービル(RSモービル)の登場は大きかったようです。
元々、The Beatlesによって為されたレコーディング革命(アーティストが好きな時に好きなだけスタジオを使用できる)により、膨らみまくるスタジオ使用料を削減するために自前のスタジオ(アップルスタジオ)を建設したことが、ライバルバンドのローリングストーンズに衝撃を与えました。特に、財政担当とも言えるミック・ジャガーに。
誰にも(本人すら)ゴールが見えない永遠に続くリフの繰り返しを求めたキース・リチャーズにうんざりしていたミック・ジャガーは、渡りに船と購入したばかりの邸宅にスタジオの建設を考えます。
その計画の中で、オリジナルメンバーでありロードマネージャーだったイアン・スチュアートがトラックの中に全てを備えたモービル・レコーディング・カーを思いつきます。
ミックの邸宅のみならず、好きな時に好きな場所、ライブ会場でさえ録音可能になります。
このアイディアに、ゴーサインが出たのは当然でしょう。
このRSモービルは、その後、数々の名盤のレコーディングで大活躍することになります。
このモービルに備えられたコンソールもまた、ヘリオス、でした。
(Rolling Stones、Led Zeppelin、Deep Purple、Bad Company、Bob Mariy、Neil Youngその他多数)
このニュースを聞いたジミーは、1年半に及んだ超長期ツアーの終了後、休養も兼ねながら、メンバー共々田舎の邸宅でゆっくり過ごしながら、RSモービルを使用して好きな時に好きなだけレコーディングするという計画を思いつきます。
ロバート・プラントとローリングストーンズ・モービル
ヘッドリィ・グランジ
ところが、偶然にもこの時使用された大邸宅「ヘッドリィ・グランジ」でのサウンドが、後々、ボンゾのドラムサウンドに決定的な個性を与えることになります。
III、Ⅳ、に収められた全18曲中、2曲を除き(III、Gallowa Pole - エディ・クレイマーミックス。Ⅳ、The Battle of Evermore - ジョージ・チキアンツ ミキシング)、全て、アンディ・ジョンズ一人による録音、ミキシングです。まずは、1970年発表のIIIより「Out on the Tile」。翌1971年発表のⅣより「Misty Mountain Hop」。
Out on the Tiles
Misty Mountain Hop
この、Misty Mountain Hopと、おそらく全く同じ方法で録音されたと思われるのが、ボンゾサウンドとしてつとに有名なWhen the Levee Breakesです。
二曲とも、ヘッドリィ・グランジの玄関ホールにセットされたドラムを、吹き抜けの階段上にセットされた二本のBeyerdynamic(ベイヤーダイナミック) M160というリボンマイクでステレオ収録され、ヘリオスコンソール内蔵のコンプレッサー、F760で強力に圧縮され録音されて、吹き抜けの玄関ホールに響き渡るドラムサウンドを、さらに強力にしたようです。
リボンマイクとは、ダイナミックマイクでありながら、コンデンサーマイク並みにフラットな周波数を持ち、その質感は、より自然です。昔から、ドラムトップに常用されていました。
Helios F760 Comp/Limitter
ヘッドリィ・グランジの玄関吹き抜け
もちろん、高い天井の洋館特有の深いリバーブ付きです。
違いは、When the Levee BreakesにはBinson Echorecというドラム式エコー(ディレイ)がかけられているところでしょうか。ドラム全体かけられた16分程度のディレイが真ん中から聞こえますね。
Binson Echorec
ジミー・ペイジ本人の言葉によると、この時、ボンゾは、真新しいLudwig社製のグリーンスパークルのセットが届いたようで、バンドのセッティングが玄関隣のメインルームで行われている最中に、待ちきれないとばかりに、玄関ホールにセットして叩き出したサウンドを耳にしたジミー・ペイジが、思わず「これだ ! これを使おう ! 」と言って録った、らしいです。
When the Levee Breakes
Misty Mountain Hop、When the Levee Breakesの2曲では、これまでと違う点がまだあります。
おそらく、マイク二本だったことが一つの理由だったと思いますが、これまでのミックスに比べて、より深くコンプレッサーが掛かっています。
それまでのコンプ処理は、音色加工というより、あくまでも、レベル抑制だったり音圧アップが目的だった気がします。
つまり。コンプを使っても、遅いアタックとリリースで、より音色変化の少ないセッティングだったと推察できます。
この逆のセッティングにすると、いわゆる潰れたコンプサウンドになり、下手すればグシャグシャの破綻したサウンドになります。
ドラムの迫力を増しながら、破綻させないためには、アタック遅めでリリース速めのセッティングになります。
この時代、迫力を出す目的としては、前回でも解説したように、どちらかというと、テープコンプや歪みを利用することが多かったように思います。例えば、初期クイーンのプロデュースを担当した、ロイ・トーマスベイカーは、歪みを扱う名人でした。クイーンのドラムを聞くと、ほとんど歪んでいることがわかると思います。
しかし、ここでは、いわゆる現代に通じるようなコンプ感を聞き取ることができます。
たまたまHelios F760がそういう音だったのか? アンディ・ジョンズのアイディアなのかはわかりません。
また、ドラムのマルチトラックテープ再生スピードを落としているようです。
再生スピードを落とすと、当然、キーが下り、それに伴い余韻も伸び、周波数特性が下がることによりアタックも太くなります。
これも、単にテンポが早い、と感じたからなのか? サウンドの迫力を出すため、なのか?
誰も発言していないので謎のままです。(秘密を知る二人のうちアンディ・ジョンズは既に他界)
(この時代、テープスピードを上下させて、キーを変更したりサウンドのニュアンスを変化させる事は頻繁に行われていました。)
もう一つ不思議に思うことは、なぜ、2本ステレオで録音しているのに、片側へ音像が偏っているんだろうか ?という点です。
当時のドラム定位は、今のように真ん中にどっしり、という概念が固定される前だとはよくわかっていますが(実験ともいうwww)、せっかく2本でステレオ収録しているのになぜ?と思うわけです。勿体無い。
いずれにしても、ボンゾが叩き出す圧倒的なサウンドと、これらすべての相乗作用により生み出されたサウンドだと言えます。
この時代のロックは、少ない機材から、ありとあらゆる可能性を引きずり出して新しい革新的なサウンドを作り出そうと、誰もが必死に切磋琢磨してサウンドを創造していたんですね。なんと素晴らしい時代!
自らマイクの位置を指差すジミー・ペイジ
ホールで手を叩きリバーブを聞くジミー・ペイジ
しかし、それにしても、たった二本でこのサウンド ! ! ! !
ボンゾだからこそ可能なサウンドです。
他のドラマーでは、なかなかこうはなりません。
まさにボンゾだけのドラムサウンドが確立した瞬間です。
この時、ジミー・ペイジも確信したに違いありません。これこそが唯一無二のツェッペリンサウンドだと。
というのも、この、いわゆるアンビエント(アンビエンス)ドラムサウンドが、この後のアルバムでも、ここ一発の場面で登場するわけですが、時代は70年代真っ只中、ドライかつクリアーで各パーツが点で見えるようなサウンドが主流の時代に、まるで、そこに立ちふさがるかのように、巨大な塊の面で押しまくるようなサウンドで最後まで勝負したのがLed Zeppelinだからです。
※アンビエンスとは、環境音の事。レコーディング用語としては、もっぱらルームサウンド(部屋の響き)の意として使われることが多い。
(しかし、このサウンドに関しては、これまで様々な憶測による解説が出てましたが、全て外れてましたねwww。例えば、ツェッペリンが宿泊していたホテルの非常階段の踊り場で録られた、とか。信じてたな〜www
しかも、意外なほど狭い。
ヘッドリィ・グランジが郊外の大邸宅と知った時も、最低でも30畳くらいの面積と、10mくらいの高さの天井を想像していましたwwww。)
皮肉なことに、80年にボンゾが天国へ召されツェッペリンも解散した後の80年代には、まるで、ボンゾサウンドを追いかけるようなアンビエントサウンドの大流行になります。
しかし、そのいずれもが、ボンゾサウンドには程遠い、と個人的には思います。
この80年代は、100chに及ぶ入力、チャンネル毎のGate&Comp、セッティングリコール等まで装備した超多機能コンソールやデジタルリバーブの登場で、多種多様なエフェクトが同時に何種類も使用することが可能になり、ルームアンビエンスと混ぜ合わせた強力なドラムサウンドが音楽シーンを席巻した時代です。それでも、原音の差は如何ともし難いものがあるのだと思います。
この当時、百花繚乱のバンドシーンの中でも異彩を放ち、たった一枚で解散したPower Stationの1985年の作品「Get It On (Bang a Gong) 」。
これ、夭折の天才マーク・ボラン率いるT-Rexが1971年に発表した作品のカバーですが、原曲同様めちゃくちゃかっこいいっす。
このバンドのドラマー、トニー・トンプソンは、あのシックのメンバーで、当時最高のドラマーの一人でした。
どうでしょう? ボンゾと比べて・・・
因みに、エンジニアは、ジェイソン・カサロ、スタジオは当然パワーステーションです。
因みついでに、このトニー・トンプソン、地球規模のチャリティーショー、USA for Africa('85)のLed Zeppelin再結成時のドラマーをフィル・コリンズと共に務めました。バンド自体の出来は散々でしたね。ジョン・ポール・ジョーンズは相変わらずの達者ぶりでしたが、なんせフロントの二人が・・・・・言うまい(T . T)
Get It On (Bang a Gong)
いよいよ、終盤です。
えっ? まだ4枚目じゃん、というツッコミはごもっともですが、この4枚を持って、ジミー・ペイジは、あらかた、自分たちにピッタリのレコーディング方法の全てを会得したのだと思います。
つまり、70年代も中盤以降になると、ロックは巨大産業化し、それに伴い、いわば先逹の弟子ともいうべき優秀なエンジニアも増え、機材も進化し、プロデューサーのサウンド志向がはっきりしているのであれば、もはや、誰と何処で録っても、望むサウンドが出せるようになったということです。
(個人的には、現代ロック(特にハードロック)エンジニアリングは、IIから担当したエディ・クレイマー、III、Ⅳを担当した、アンディ・ジョンズ、それと、ツェッペリンとは一切関わりありませんが、ディープ・パープルやレインボー、アイアン・メイデン等を担当したマーティン・バーチの三人によってその基礎が形作られたように思っています。あっ、ビートルズの、ジェフ・エメリック入れないといかんですね〜。それとT-Rexではエンジニア、クイーンではプロデュースを担当したロイ・トーマス・ベイカーとクイーンやジャーニーのエンジニア/プロデューサーを務めたマイク・ストーンも忘れちゃいけませんね。
えーっと他にも・・・人数限定は無理っすねwwww)
Ⅳの次の「永遠の詩」は、再度エディ・クレイマーを起用していますが、続く、「フィジカルグラフィティ」も、一曲を除き(「House of Holy」録音ミックスともにエディ・クレイマー)、録音は、エンジニア、場所は様々ですが、ミックスエンジニアは、全てキース・ハーウッドが担当しています。
(個人的には、House of Holyのサウンドが一番好きですがwww)
「Presence」では、前作に続き、キース・ハーウッドが録音ミックスの全てを担当していますし、スタジオもドイツのMusiclandを使用しています。
それでも、サウンドの個性はまさにツェッペリンそのものです。
ここでは、「フィジカルグラフィティ」から、「Kashmir」。録音場所は、あの、ヘッドリィ・グランジ、エンジニアは、ロン・ネヴィソン。まさにここ一発のサウンドを使ってます。が、よく聞くとわかりますが、当然録音方法は違っています。
おそらく、各パーツ毎にクロースマイク(オンマイク=近接マイク)をセットした上で、離れた場所に置いたアンビンエンスマイクを立てて録音し、軽くフランジャーかフェイザーを掛け、ミックスするというまさに現代的な手法で仕上げられていると思います。
それでも、ボンゾはボンゾです。
では、「フィジカルグラフィティ」から「Kashmir」続けて「Presence」より「Nobody's Fault but Mine」
「Kashmir」
「Nobody's Fault but Mine」
ミックスエンジニアが同じということもありますが、実によく似たサウンドになっていますね。
この時のエンジニア、キース・ハーウッドは、多忙のあまり、77年に居眠り運転で事故死されます。まさに売れっ子エンジニアになって、さあこれからという時でしたのでさぞや無念だったことでしょう。
書きながら思い出しましたが、80年代といえば、1988年にツェッペリンにまつわるちょっとした騒ぎがありました。
ある日のFMから突然流れてきたある曲が、「Kashmir」そっくりだったんです。
特に、リフとボーカル ! ! 一瞬、プラントの喉が治って再結成したのかと思ったほどです。しかも、その番組のホストは、あの熱狂的ツェッペリンフリークで有名な渋谷陽一氏だったので尚更です。
既に、世界的に話題沸騰中だったようです。
この騒動の主は、Kingdom Comeという新人バンドでした。
プロデューサーは、カナダ人のボブ・ロック。
彼は元ギタリストですが、サバイバーやラヴァーボーイ、エアロスミス等のエンジニア活動を経て、プロデューサーになった人で、メタリカやモトリークルーの大ヒットで大成功を収めます。エンジニアとしてもプロデューサーとしても大変優秀な人のようです。
サウンド傾向は、80年代を象徴する派手でエフェクトたっぷりの、まさに産業ロックそのものです。貶しているわけではありません。プロの世界は売れてナンボです。
意外なところでは、スタンダードジャズボーカルの旗手、マイケル・ブーブレも担当しているところです。個人的に大好きなシンガーです。
スタンダードジャズだけでなく、懐かしい感じのR&Bや、ビートルズっぽいポップスまで幅広いスタイルの持ち主です。懐の深いプロデューサーなんですね。
また脱線しました。😓
Kingdom Comeは、その余りにツェッペリンを彷彿させる曲調とボーカルによってか、世界中で大ヒットしました。
ところが、内容も演奏も中々良かったにも関わらず、結局似過ぎていた事が仇となり、叩かれるだけ叩かれて、結局2枚のアルバムを出しただけで消えて行きました。
神に近づき過ぎると火傷するということなのでしょうか ?
まるでイカロスのように?😆
このバンドのドラマーはなかなか優秀だったようで、その後も、様々なバンドで活躍したようです。(2016年まで、スコーピオンズに在籍)
まさに産業ロック全盛の80年代末期にあらゆるスタジオ機材を駆使して挑んだツェッペリンサウンド、お楽しみいただければ幸いです。
KINGDOM COMEファーストから「Get it On」
「Get it On」
いかがでしょうか ? www
HR/HMバンドしては十分かっこいいと思うんですけどね・・
この曲以外にも、あれ? Since I've ・・? とか、おっ、Battle of ? とか、思わずニヤリとさせられる曲もありますので、大きな心で楽しみたいと思う次第です。☺️
この曲以外にも、あれ? Since I've ・・? とか、おっ、Battle of ? とか、思わずニヤリとさせられる曲もありますので、大きな心で楽しみたいと思う次第です。☺️
さて、いよいよオーラスです。
ここまでくると、なぜ、ジョン・ヘンリー・ボーナムこそがロック史上最高のドラマー、という自論を持つに至ったのか、なんとなくご理解いただけたのではないでしょうか?
彼のドラムサウンドは唯一無二(しかも、世界中のロックドラマーが憧れ追求しているにもかかわらず誰も近づけない)かつ、同時にバンドそのものを体現しました。
こんなドラマーとバンドは、もう二度と出ないでしょう。
もちろん、彼より上手いドラマーなどいくらでもいるでしょう、違う意味で素晴らしいサウンドのドラマーも。
しかし、誰一人として彼のような並外れたサウンドは出せません。
彼のように、自らのサウンドがバンドサウンドを体現したドラマーも思い当たりません。
故に、彼をしてロック史上最高のドラマーだと思うのです。
最後に、彼ら最後のオリジナルアルバム「In Through the Out Door」('79)より、彼が敬愛したドラマー、バーナード・パーディー(単にドラマーとなれば、No1の筆頭)がプレイしたスティーリー・ダンのアルバム「Aja」収録の「Home at Last」(カッケー!)にインスパイアされたといわれる「Fool in the Rain」。
因みに、この二曲に、TOTOの名ドラマー、ジェフ・ポーカロがインスパイアされて生まれたのが「Rosanna」だということは有名な話。
(久しぶりに聞いた「Home at Last」があまりにかっこよかったので、これも添付します)
Fool in the Rain
Home at Last
レコーディング、ミキシングともにエンジニアはレイフ・マセス。
スタジオは、レコーディングがポーラー・スタジオ。ミキシングが、プランプトン・スタジオ。共にスウェーデンです。
このサウンドが、When the Lebee Breakesと並んで、ボンゾサウンドの代名詞だと言われているようですが、もはや、イギリスのスタジオでもエンジニアでもありません。
かくて、最後のアルバムにしてジミー・ペイジ プロデュースはついに確立したのです。
※ あくまでも個人的見解ですが、Led Zeppelinとは、まさにそのサウンドそのものが本体なのだと思います。勿論、メロディやアレンジ、詞、演奏こそが音楽ではないか ! というごもっともなご意見にも大いに賛同しますが、Led Zeppelinに関しては、これだけでは当てはまらないと思います。
デビュー当時から散々批判された、ブラックミュージックからの、詞、メロディ等の限りなくアウトに近い引用(パクリともいう)の数々(裁判ではかなり敗訴したらしいwww)。
しかし、比べてみれば一聴瞭然、その圧倒的サウンドにひれ伏してしまうのです。
まさに、誰にも出せないサウンドがそこにあります。
勿論、バンドの成長とともに楽曲も大いに発展を遂げ、Ⅳの頃には、これぞLed Zeppelinという楽曲が生まれていました。
それでも、ツェッペリンの本質はサウンドであると確信します。
そして、その中心にいたのがボンゾのドラムでした。
もし、この駄文を最後まで読んでいただいた方がいらっしゃったのでしたら、心から感謝申し上げます、ありがとうございました。
これに懲りず、また覗いてやってください。相も変わらずマニアックネタだとは思いますがwww







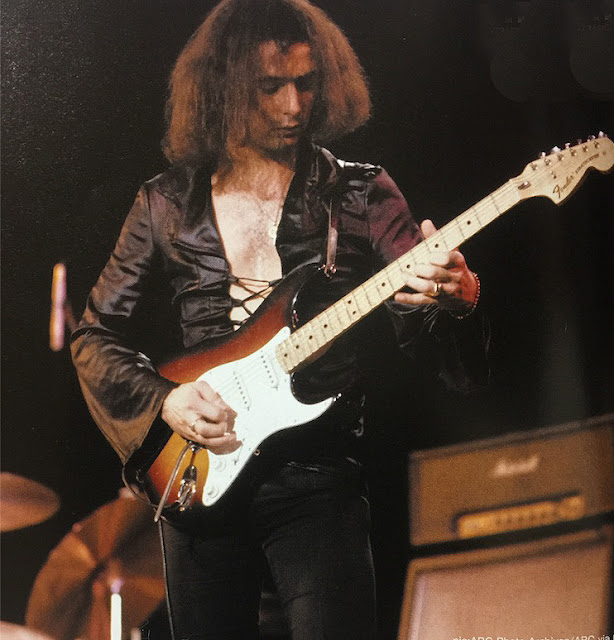


コメント
コメントを投稿